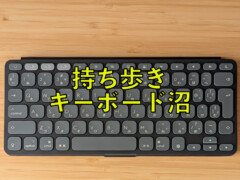万城目学さんの『ザ・エッセイ万博』に
「万博に行ってきた」と人に言うと感想を聞かれ
「楽しかった。疲れたけど。暑かったけど」
というと、みんな行きたがる
けれど行かないだろう
というようなことが書かれていました。
結局のところ、僕も
行かない側の人間になってしまいました。
4月の早々に行こうと思った週に
クライアントの予定に合わせて
泣く泣く中止
で、そこから結局いけずじまいでした。
こんちくしょう。
万博は未来のウンタラカンタラ
という名目があるはずで
そういう点であの大屋根リングが
未来の建築を示しているのか?
(あるいは、建築ではなくても何かの未来)
というのはずっと疑問があって
(僕自身は貫工法に未来を感じますが
社会は感じてないよね?)
それを実感しに行きたかったけど
仕方ねえなあ〜
チャーチルの有名な言葉で
私はタマゴを産んだことは一度もありませんが、タマゴが腐っているかどうかは分かります
というものがあります。
私は万博へ行ったことはありませんが
万博が…おっと、やめとこう。
負け惜しみにしか聞こえませんね。

最初はドキモいと思った
ミャクミャク様もすっかり慣れた
慣れって怖いね
しかしまあ、万博は
行ってきた、とSNSとか
ブログに書くためのものではなく
そこから未来をどう考えられるか
それに尽きると思っています。
そして、建築という面に関して
どうだったんでしょうね?
まあ、見てないし
見たからってわかるかというと
定かでありませんけれど。
前評判とは打って変わって
連日盛況、と言われた今回の万博ですが
1970年の万博では
入場者数は約6422万人
当時の日本の人口は約1億372万人
ということは
単純に割ると人口の62%ぐらいの
入場者があったということです。
今回の万博は
推計約2820万人・人口約1億2330万人
割合は23%ぐらい。
露出した写真の数は
おそらく今回の方が圧倒的に多いですが
実際に行った人は半分以下
70年の万博が
いかに国民的行事だったか
(そして、たぶん、それをまた望んだ人が
今回の万博を誘致した)
そういう点では冒頭の万城目学さんの
指摘は図らずも当たっているような
関心がある人はあるがない人には全然ない
もうみんな万博に行ってるように
見えてしまったとしたら
フィルターバブルってやつ?
前回の万博の頃には土曜の夜には
みんな「八時だよ 全員集合」を
見ていた(50%超えの視聴率を記録)
そんな時代ではないわけです。
消費構造は変わっているし
住宅に求められるものも
(良し悪しは別として)
ずいぶん変わりました。
この多様化の時代に
それでもマジョリティを目指すのか
マイノリティの道を極めるのが良いのか
万博はそんなことを教えてくれました
とか綺麗にまとめてみたよ
ああそうだよ、行けなかった負け惜しみだよ!