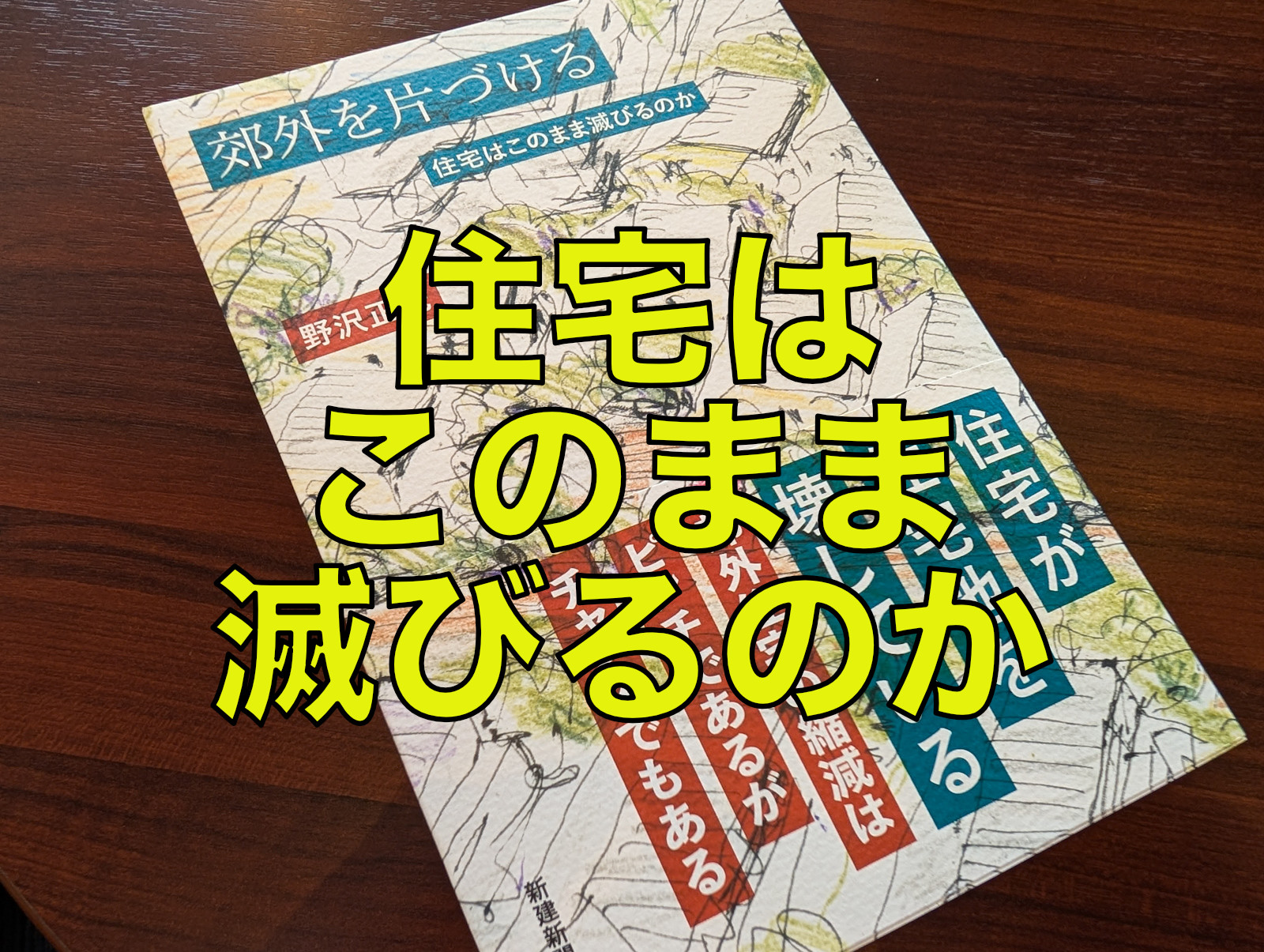2023年に亡くなった
建築家・野沢正光さんが
生前に書かれたものがまとめられ
出版されました。
『郊外を片づける 住宅はこのまま滅びるのか』
新建新聞社刊
帯にでっかく書かれている
住宅が住宅地を壊している
という言葉
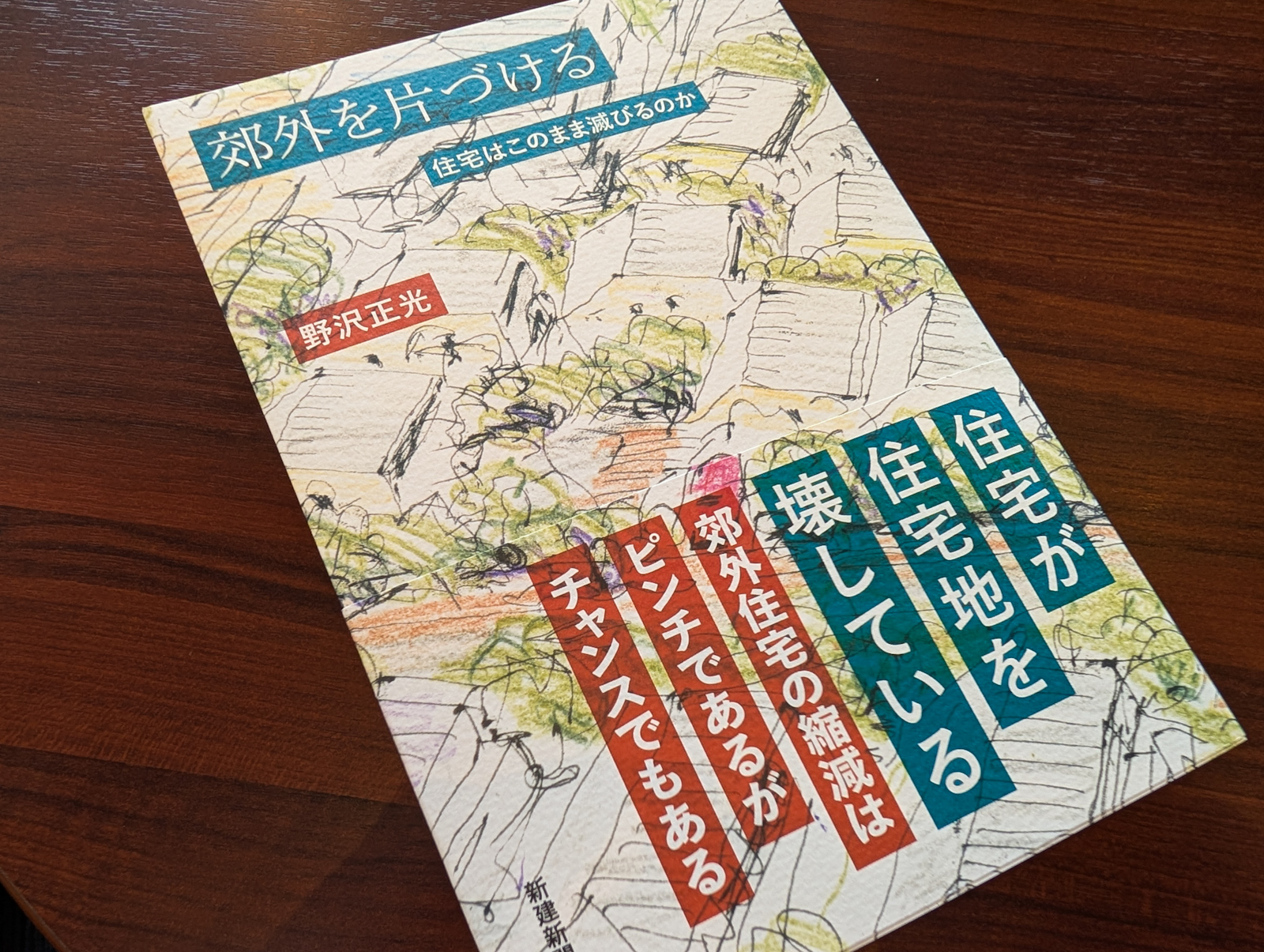
これに少しでも後ろめたさを
感じる人は
壊していることを反省してもらい
なんのことかさっぱりわからない
という場合は
壊してますね…多分…
やっぱり反省してください。
本書の訴えで
心に残った…というか
ぜひ工務店の皆さんにも
心していただきたい言葉が
高性能住宅の優遇措置が劣悪な風景を生む
ということ
最小限の敷地に最大限で建て
庭がなく道路からすぐ丸見えの家では
外からは遮断して設備だけで
室内環境を作らないといけない
これが賢い家のように
昨今では言われていますが
僕は貧しいことだと思います。
行政が主導しメーカーが乗った
ということなんだろうなあ…
住まいの寿命が短くなったのは
相続とか耐用年数の問題もあるけれど
ものがすぐに壊れたりして
売る側は都合がいいけれど
住む側には迷惑な状態が放置されていて
この国の住宅の寿命を決めているのは怒ることをしない私たち消費者が原因であるのかもしれない
という言葉に、またしても
後ろめたさを感じるのです。
野沢さんとは
浜松駅の改札で偶然お会いしたのが
最後になってしまいました。
こういうお話を聞く機会も
なくなってしまったのかと思いましたが
こうして本という形で触れることが
できるのはありがたい限りです。
野沢さんは
OMソーラーの誕生からその後の発展まで
大きく関わった方でもあるので
本書でもOMソーラーが果たした
役割についても触れられています。
それは温熱環境がどうこう
という話ではなくて
工務店が学んでいく萌芽というか
そんなことが記されています。
まあ、そういうことは
大多数の読者にはもはや
関心が薄いのかもしれません。
とはいえ決してノスタルジーの本ではなくて
現在起こっている問題について
触れられているものです。
一方で、郊外を片づけるということは
容易ではないなあ、ということも
改めて浮かび上がってしまうのですが
住宅は個人のものであると同時に
社会財である
ということは
何十年も地域に残り続けるんだから
当たり前のはずなのに
ほとんど忘れられている気もします。
そういう意識を取り戻すためにも
ぜひ本書を読んでいただきたいと思う次第です。