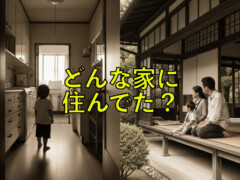連日あちこちで猛暑の報道
気温だけじゃなくて湿度も大切だぞ〜
と言ってはいるものの
湿度が高くても死なないけど
温度が高いと命に関わるからな…
ペットボトルとかあまり買いたくないので
お出かけの時には水筒を持っていきます。
(水筒に酒を入れていると疑われることが
多いですが、大抵、水です)
冷蔵庫で冷やした水を入れておくと
一日中冷えていてありがたや〜
(冷たい水は体に良くないという話もあるけど)
住宅の断熱を表現するときに
「魔法瓶のような家」
という言い方をしているのを見かけます。
魔法瓶のような家って
こういうのか…?

ではなくて
断熱されているということの比喩
なんだと思いますが
魔法瓶の断熱は
瓶が内外で二重になっていて
その間は真空
これで伝導と対流による
熱を防ぎ
内部はステンレスとか
ガラス面へのメッキで
輻射熱を反射させている
となると
真空断熱材を使って
遮熱材も併用していれば
魔法瓶みたい
ってことになるのかな?
(あと、窓がなければ)
大抵の場合「魔法瓶のような」
という言葉にはそこまでの意味は
こめられていなくて
通常の充填断熱材・遮熱材なし
という場合が多い…かも
つまり、断熱してあると
中の温度を保ちやすい
というぐらいのことなんだろうと
思いますが
そういう表現をしていると
僕みたいな客が来た時に
突っ込まれちゃうぞ
…ではなくて
20代、30代の施主さんに
「魔法瓶」って言葉、通じるのかな?
タイガーとか象印みたいに
社名に魔法瓶を冠している
会社もありますし
(象印はマホービン)
「まほうびん」というJISも
制定されています。
そういう意味では
もちろん現役バリバリの言葉なんだけど
ワカモノの皆さん、どうなんでしょう?
「魔法瓶」って何かわかる?
なお、魔法瓶のような構造だと
内部の温度を一定に保とうとする
わけですが
熱は必ず高い方から低い方に流れるので
暖かい飲み物はいつか冷めますし
冷たい飲み物はいつかぬるくなる
家で考えたら、これじゃ困りますよね。
冬は家電や人体の内部発熱があるので
魔法瓶的発想でも温度が保てる可能性がありますが
夏も同様に熱源があるので
断熱・遮熱だけでは室内温度は上がる一方です。
冷房という冷熱源があることで
その温度を保ちやすくなる
ということではありますが
構造はやっぱり割と違うし
ワカモノに通じるかわかんないし
少なくとも僕は
「魔法瓶のような家」
という表現は使いたくないな〜
という具合に
今週もめんどくさく行きます!