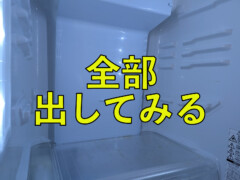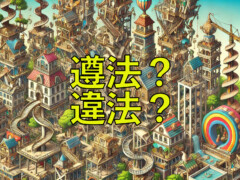昨日の
冷蔵庫の中ぜんぶ出す! には
大反響をいただき(一部嘘)
やっぱり色々なことに
再構築(restructuring)が
必要だな〜と痛感する一方で
手放せる・手放せないって
一体何なんだろう…
役に立つ、立たないだけじゃなく
気に入っている
手放し難い、という感情
これは意外とお仕事にも
関係あったりして
なんて思う次第です。
その思いを加速したのは
書籍『人はなぜ物を愛するのか
-「お気に入り」を生み出す心の仕組み-』
物、とされていますが
原題は『The Things We Love』
Thingsは日本語だと
「モノ」にも「コト」にも訳せる
万能な言葉なので
人はなぜ何かを愛するのか
ぐらいの感じだろうか?
でも本文では「モノ」と書かれてるので
以下「モノ」でいきますね。
(住宅の例もちょーっとだけ出てきます)
本文中にも登場する愛とは
自分の生活と深く絡み合っている相手に対して感じる好意とやさしさ
ハワイ大学のエレイン・ハットフィールドとリチャード・ラプソンの示した愛の定義
この「相手」というのは
時に人であり時にモノであり
でもモノを愛するときに
それは単にモノを愛するだけでなく
人とのつながりをも求めている
みたいな話がこの本の根底にあります。
モノを愛する時
人ーモノ
という結びつきに見えるけど
関係をよくみると
人-モノー人
という繋がりがあるという。
建築中の現場を
よく見に来ていたお客さんが
あの大工さんが作ってくれた
というような感動を覚えるのも
家というモノを通じて
人ーモノー人
が実現できている例ではないでしょうか。
(もちろん、その大工さんだけでなく
多くの人がつながっているので
人ーモノー人々、でもある)

じゃあ、たとえば僕が
毎日使っているスマホやPC
これらも
自分の生活と深く絡み合っている相手
ではありますし
愛着がないわけではないけど
新しいものを買うと
すっかり興味は
新しい方に向かってしまいます。
これは愛…なのかな?
どうも、これは愛というより
利益をもたらす価値を認める
ということらしい。
愛はそれにとどまらない
情動的なものだ、と。
前に紹介した↓
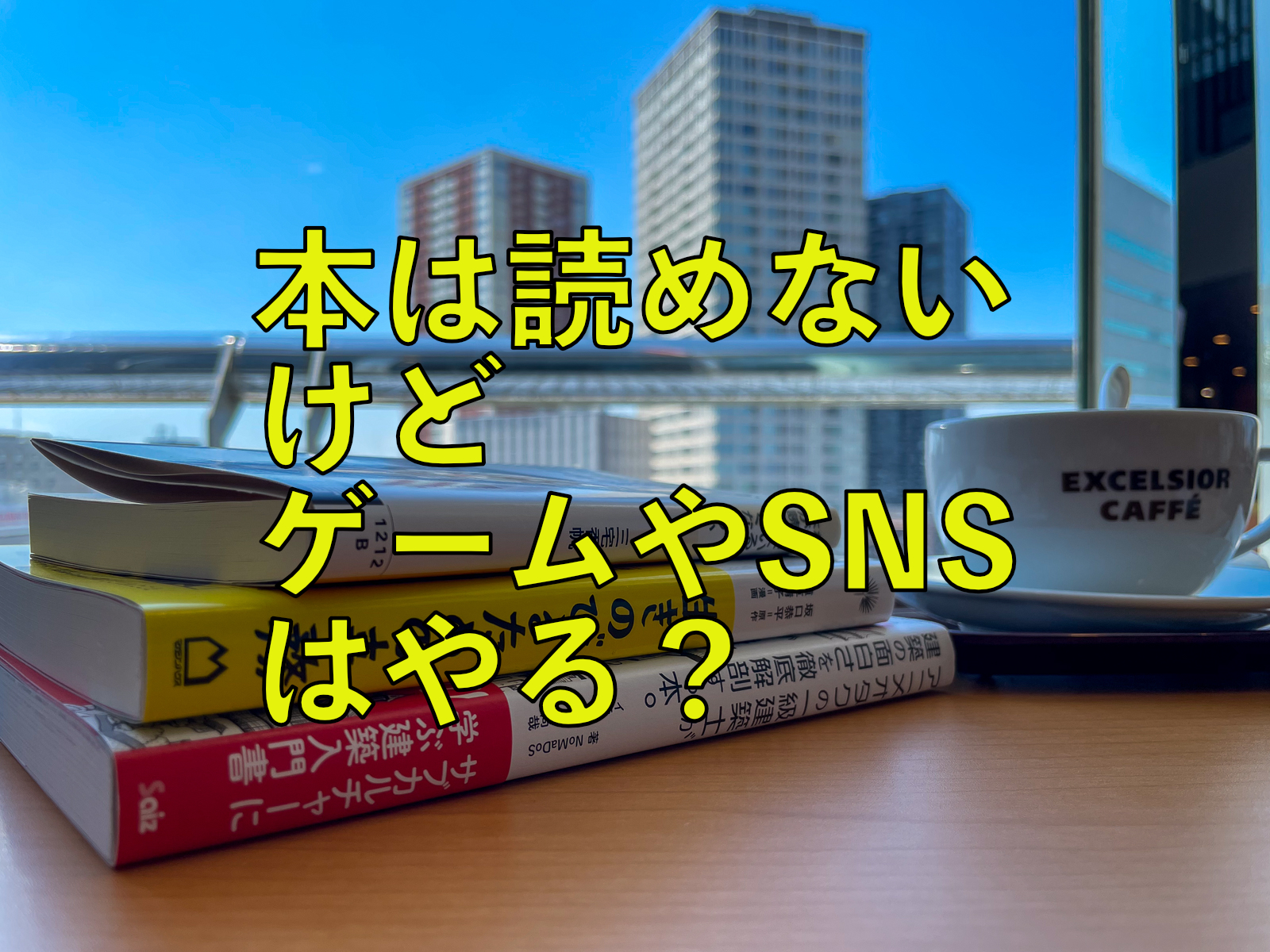
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』
にあった
ノイズ込みの知が読書
ノイズを除去した知が情報
というのに似ているかな?
愛とノイズが似ている
なんていうと
おかしいかもしれないけど
利益の価値≒情報
愛≒読書
って書いたらわかりやすいのでは?
(余計わかりにくくなった気もするな)
とにかく、つまり!
スペックを並べたて
住まい手にどんな利益がある
ということだけをいう
住宅の売り方では
利益の価値は伝わっても
愛されない
かもしれない。
それを愛に昇華するには
やっぱり作り手の思いが
きちんと伝わらないと!
愛してもらえば
ちょっとぐらいのことは
クレームにならない…
みたいな打算は置いといて
モノ(住宅)を通じて
人と人がどうつながるのか
これを可能な限り伝えていく
というのが
魅力に映る方法ではなかろうか。
素敵な世界を作っている
工務店はことごとく
そんなやり方をしていると
改めて気がつきました。
うまく行っていないあなたは
愛が足りません!