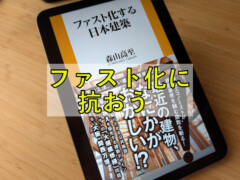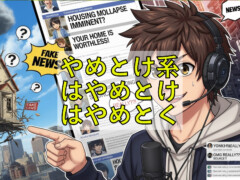昨日は浜松市でも40℃超え。
もう「予報が35℃ならホッとする」なんて
おかしな感覚になってきました。
40℃を超えた14:45の直前
14:40のアメダスを見てみると
気温39℃・湿度36%。
このときの絶対湿度はおよそ17.5g/㎥。
数字だけ見ると「カラッと暑い」状態です。
同じ時刻、うちの外気温計は39.6℃・湿度40%。
絶対湿度にすると約20g/㎥。
Amedas地点と我が家はそう遠くないですが
湿度が高いですね。庭に木がたくさんある影響かな。
数値で見ると湿度が高いのでより不快
というはずですけど
木陰はまあまあ快適です。
ほんと、温度だけでは評価しづらいよな〜
日射遮蔽のことは何度も書いてきたし
HEAT20でもG-A、G-Bといった
開口部日射遮蔽への動きも出てきました。
しかし、この基準でも
冷房顕熱負荷を減らす
というのがテーマです。
冷房顕熱負荷というのは言ってみれば
温度を上げる要素です。
これが潜熱負荷になると
水蒸気が持っている熱が対象になります。
ちょっとややこしくなってきちゃいましたね。
顕熱が下がると温度は下がるけど
潜熱は下がらず湿度は下がらない。
最近、高断熱住宅で起きる
エアコンがすぐ設定温度に達してしまい
室温は下がったけど湿度は下がらない
ということがありますが
冷房顕熱負荷だけを見たら
これでOK、ってことになるわけです。
ところが水蒸気は潜在的な熱を持っている。
ので、人によっては不快に感じるかもしれません。
温度はもう猫も杓子も言っている状態ですが
湿度のことをちゃんと言っているケースは
かなり少ないので
そこにチャンスがある、かもしれません。
湿度のことはよく間違えて捉えられていて
たとえば珪藻土
霧吹きで水をかけて
「よく吸いますよね、すごいでしょ!」
というデモをやったりします。

でもそれは“液体の水”を吸っているだけで
“水蒸気の出し入れ=調湿”とは別の話です。
液体の水が気体の水蒸気の出入りを
阻害することさえあるはずですが
まあそれは置いといて
本来の調湿建材の役割は「バッファー」。
急激な湿度変化をやわらげてくれる存在です。
劇的に数値に影響するわけではなくても
この差が暮らし心地に効いてくる、んだけど
省エネ基準にもHEAT20にも
湿度に関する基準はありませんから
数値命・基準命の人には
関心が薄いかもしれません。
何より、湿度は体感の個人差が
温度以上に大きい
(ように思います。個人の感想です)
その上、生活スタイルによっても
発生量が全然違います。
毎日湯船にお風呂を張って
洗濯物を室内干しして
毎日煮炊きしている人と
さっとシャワーで済ませて
洗濯は外干し
料理は外食や中食だったりする場合とで
水蒸気の発生量が全然違う
というのは
なんとなくわかるかと思います。

こんなヤツいねえよ〜
という絵ができたけど
これはこれで面白いので置いとく。
じゃあ工務店が湿度の話をどう武器にするのか。
全熱交換型の一種換気で湿度をコントロールする
というのもありだろうし
三種換気+調湿建材のバッファー的要素は
木の家の居心地の良さ、の延長線上にあり
こっちの方がしっくりくる会社も多いかも
どちらにしても
設備や建材のメーカーがいうことを
意味もわからず営業トークするんじゃなくて
自分たちが考える家づくりがどういうもので
それにあっているからこれを選んだ
というお話が必要なんだろうな〜
という話は
日曜恒例お料理ネタを考えていて
しかし今日はちょっと料理をサボったので
キッチンの水切りカゴの下に置いてある
珪藻土バスマットを見て
そんなことを思いついたのでした。
料理しないと室内の温湿度が落ち着いてる
我が家の一番の冷房潜熱負荷は料理だなあ…換気扇の性能不足かなあ